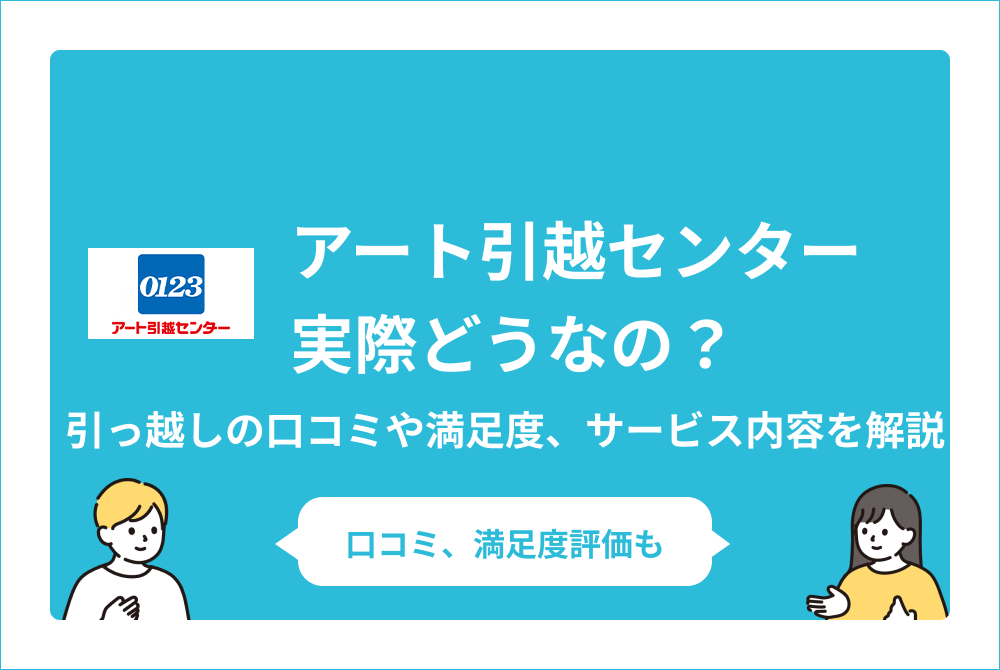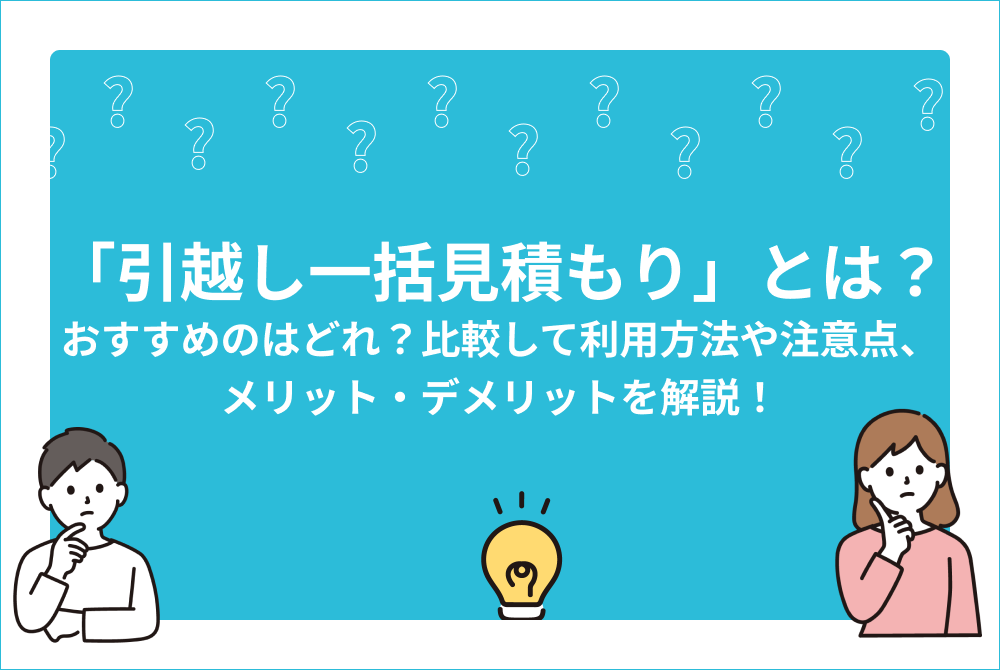目次・一覧
生活保護を受けている方の中には、今の住まいのことで悩んでいる方がいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時、真っ先に気になるのが、費用が出るのか、手続きは難しくないかという点ですよね。生活保護を受けている方の場合、条件さえ満たせば引っ越し費用を受け取ることができます!
この記事では以下について解説します。
- 生活保護受給者の方が引っ越し費用を受け取るための条件
- 引越し費用を受け取るための手続きの流れ
- 引越し費用の節約術
住まいは生活の基盤となる大切なものです。生活保護を受けているからと諦めず、安心で快適な暮らしをスタートさせましょう。
生活保護受給者の引っ越し、費用が出る条件とは?
憲法で全ての国民に対し、居住・移転の自由が認められているため、生活保護受給者も自由に引っ越しを行うことができます。また一定の条件を満たせば、国から引っ越し費用が支給されます。支給される費用は、賃貸の契約費用と引っ越し業者の運搬費用であり、引っ越しを行ううえでどうしても必要な費用のみとなっています。
しかし、残念ながら、誰もが必ず引っ越し費用を受け取れるわけではありません。費用が支給されるには、主に次の3つの条件を満たす必要があります。
事前に福祉事務所に相談・許可を得ている
引っ越し費用が支給される最も重要な条件は、自治体の福祉事務所から許可を得ることです。引っ越しを考え始めたら、必ず引っ越しをする前に、福祉事務所のケースワーカーに相談してください。事前の相談なしに、勝手に引っ越しをしてしまうと、引っ越し費用が支給されない可能性があります。
相談の際には、引っ越しを考えている理由や、現在の住まいの状況、引っ越し先の希望などを具体的に説明しましょう。ケースワーカーは、提供された情報をもとに、引っ越しが必要かどうか、費用が支給されるかどうかを判断します。
やむを得ない理由がある
そして一般的に福祉事務所から許可が下りるケースとしては、引っ越しを行う「やむを得ない理由」があることです。具体的には、次のような理由が挙げられます。
- 住居の問題:
- 人数に対し現在住んでいる家が狭すぎる場合
- 家賃の値上がりにより、より安い家賃の家へ引っ越したい場合
- 立退きを求められた場合。
- 災害による現在の住居が住めない状態になった場合
- 老朽化等により現在の住居が住めない状態になった場合
- 現在の住まいが病気等の療養に適していない場合
- 現在住んでいる家が取り壊される予定になっている場合
- 家主から契約更新の拒否・解約の申し入れがありやむを得ず引っ越す場合
- 生活上の問題:
- 入院患者が退院後に住む住居がない場合
- 失業により社宅から退居した後に住む住居がない場合
- 社会福祉施設などから退所した後に住む住居がない場合
- 現在の住居からの通勤が困難なため、職場の近くへ引っ越す場合
- 居候していた人が転居後に住む住居がない場合
- 離婚により新たな住居が必要な場合
- 社会的な問題:
- 被保護者が適切な法定施設に入居する必要がある場合
- 介護をはじめ社会福祉サービスや支援を受けやすい地域へ引っ越す必要がある。
これらの理由以外にも、個々の状況によって「やむを得ない理由」と認められる場合があります。まずは、お住まいの地域の福祉事務所に相談してみましょう。
1-3. 引っ越し先の住居が一定の条件を満たしている
引っ越し先の住居にも、いくつかの条件があります。主に次の条件を満たす必要があります。
- 家賃が住宅扶助の基準内であること:生活保護には、住宅扶助の上限額が定められています。引っ越し先の家賃が上限額を超えている場合、費用が支給されない、または一部のみの支給となる可能性があります。
- 住居が最低限の基準を満たしていること:広さや設備などが、福祉事務所が定める最低限の基準を満たしている必要があります。
- 保証人を確保できること:賃貸契約を結ぶ際に、保証人が必要となる場合があります。保証人を確保できない場合は、福祉事務所に相談しましょう。
住宅扶助額は各自治体で地域・部屋の広さごとに決められています。下記は単身者の条件で各自治体で設定されている住宅扶助額の目安です。
| 自治体 | 住宅扶助額 |
|---|---|
| 北海道(札幌市内) | 3.6万円 |
| 宮城県(仙台市内) | 3.7万円 |
| 東京都(23区内) | 5.3万円 |
| 愛知県(名古屋市内) | 3.7万円 |
| 大阪府(大阪市内) | 4.0万円 |
| 広島県(広島市内) | 3.8万円 |
| 福岡県(福岡市内) | 3.6万円 |
※費用相場はあくまで目安です。
※賃貸の森『生活保護受給者は引越しできるの?[生保の引越しマニュアル]』より参照(2025年3月調べ時点)
基本的に住宅扶助額を超えない範囲で新居をさがすと良いのですが、東京都の23区内など、地域によっては住宅扶助額以下の物件を探すのが難しい場合があります。自治体によっては住宅扶助額を超えた物件の居住を認める場合があります。その際は住宅扶助額上限の1.3倍に設定された特別基準額の範囲内におさめるようにしましょう。
引っ越し先の住居が適切かどうかについても、事前に福祉事務所に相談し、確認してもらうことが大切です。
【図解】生活保護で引っ越す際の流れ:相談から入居まで
生活保護を受けて引っ越しをする際の流れは、次の5つのステップで進みます。
ステップ1:福祉事務所に相談
まず、福祉事務所のケースワーカーに、引っ越しを検討していることを相談します。引っ越しの理由や現在の住まいの問題点、引っ越し先の希望などを具体的に伝えましょう。
ステップ2:福祉事務所の許可を得る
福祉事務所は、提供された情報や住居の状態を調査し、引っ越しの必要性や費用支給の見込みを判断します。許可が下りたら、引っ越しの準備に進みます。
ステップ3:引っ越し先の住居を探す
不動産情報サイトや不動産会社で、引っ越し先の住居を探します。福祉事務所から提示された住宅扶助の上限額内で、条件に合う住居を見つけましょう。分からないことがあれば、不動産会社や福祉事務所に相談しながら進めると安心です。
ステップ4:福祉事務所に住居の情報を提供、最終確認
引っ越し先の住居の候補が見つかったら、家賃や間取り、初期費用などの情報を福祉事務所に提供し、最終確認を受けます。福祉事務所は、住居の妥当性や契約内容などを確認し、問題がなければ引っ越しと賃貸契約の手続きに進みます。
ステップ5:引っ越しと入居
福祉事務所の許可と住居の最終確認が得られたら、引っ越し業者を手配し、引っ越しと入居を行います。引っ越し後も、福祉事務所と連携を取り、新しい生活をスムーズにスタートさせましょう。
福祉事務所への相談から引っ越し、入居までは、およそ1ヶ月程度の期間を見ておくとよいでしょう。引っ越しシーズンは、福祉事務所や不動産会社の混み具合によって期間が変動します。早めに計画を立てて進めることが大切です。
2-1.引越し費用はどこまで出る?各ステップごとの注意点
ステップ1・ステップ2
- 区外・県外への引っ越しは慎重に:可能ですが、通常の引っ越しよりも審査基準が厳しくなります。また、引っ越しにより自治体が変わるため、担当の福祉事務所も変わります。その際に現在と同じ生活保護水準で対応してもらうため、移管作業を行いますが、ほとんどの場合は引っ越し先の事務所で再度生活保護の審査を行います。結果によっては今までとはことなる対応になる場合もあるので、区外・県外の引っ越しは慎重に検討しましょう。
ステップ3
- 住宅扶助は一部対象とならないものがある:住宅扶助は主に家賃全体が対象となりますが、管理費や共益費などは家賃としてカウントされないため対象外となります。物件を探す際は管理費・共益費が少額のところを探すようにしましょう。
- 生活保護受給者であることは隠さずに伝える:生活保護受給者は賃貸の入居審査に通りにくい傾向にありますが、隠してしまうと後々のトラブルの原因になります。生活保護の申請同行サービスを行っている企業もあるので、どうしても入居審査に通らない場合は利用を検討してみましょう。
ステップ5
- 引越し業者は最も安いところへ:引越し業者の利用料金は、引っ越しを行ううえで最低限必要な費用に含まれるため基本的に全額支給されますが、原則最も安い引越し業者にのみ依頼することができます。なおサービス内容についても必要最低限のもののみが支給範囲となり、引越し業者が提供する荷造りや不用品処分などのオプションサービスは対象外となります。
- 引っ越し後に必要となる最低限の家電製品も支給対象:支給対象となるのは生きていくうえで最低限必要なものとされています。主にカーテン、ガスコンロ、照明器具、エアコンが対象となります。なお近年の異常気象を受け、エアコンに引っ越し費用については新たに支給対象となっています。
生活保護受給者が引っ越し費用を抑えるための5つのコツ
引っ越し費用は、できる限り抑えたいものです。生活保護受給者の方が引っ越し費用を抑えるためのコツを5つご紹介します。
部屋のサイズを見直す
一般的に、住居の広さが小さくなるほど引っ越し費用は安くなります。一人暮らしや母子家庭の場合、ワンルームや1DKなど、必要最低限の広さの住居を検討することで、引っ越し費用を抑えることができます。
引っ越しシーズンを避ける
引っ越し業者の料金は、時期によって大きく変動します。一般的に、新年度の前後にあたる3月〜4月、異動などによる引っ越しが増加する9月〜10月は引っ越し需要が高く、料金が高くなる傾向があります。これらの時期を避け、閑散期に引っ越しを行うことで、費用を抑えることができます。
複数の引っ越し業者から見積もりを取る
引っ越し業者によって、料金体系やサービスが異なります。複数の引っ越し業者から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討することで、よりお得な引っ越し業者を見つけることができます。インターネットの一括見積もりサイトを利用すると、簡単に複数の引っ越し業者から見積もりを取ることができます。
自分でできることは自分で行う
荷造りや荷解きなど、自分でできる作業は自分で行うことで、引っ越し業者に依頼する作業量を減らし、費用を抑えることができます。梱包材は、スーパーマーケットやドラッグストアなどで無料のダンボールをもらうか、100円ショップで購入するなどして、費用を抑えましょう。なお身体的な理由から荷造りが難しく、引越し業者のサービス利用を検討したい場合は、引越し費用の支給対象となるか、福祉事務所へ相談してみましょう。
福祉事務所に相談する
福祉事務所には、引っ越し費用について相談できる場合があります。福祉事務所によって、支援制度の内容や有無が異なるため、事前に確認してみましょう。また、引っ越し業者の紹介を受けられる場合もあります。福祉事務所と連携して、利用できる支援制度を最大限に活用しましょう。
まとめ
生活保護受給者の引っ越しについて、費用が出る条件や手続きの流れ、費用を抑えるコツを解説しました。
今回の重要なポイントは次の3点です。
- 生活保護受給者でも、やむを得ない理由があれば引っ越し費用が支給される可能性がある
- 引っ越し前に必ず福祉事務所に相談し、許可を得る必要がある
- 部屋のサイズを見直す、引っ越しシーズンを避けるなど、費用を抑えるコツを活用する
引っ越しは、新しい生活のスタートです。福祉事務所と連携しながら、計画的に進めることで、不安を解消し、スムーズな引っ越しを実現できます。
執筆者

DOOR賃貸編集部
DOOR賃貸運営事務局






















.png)






.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
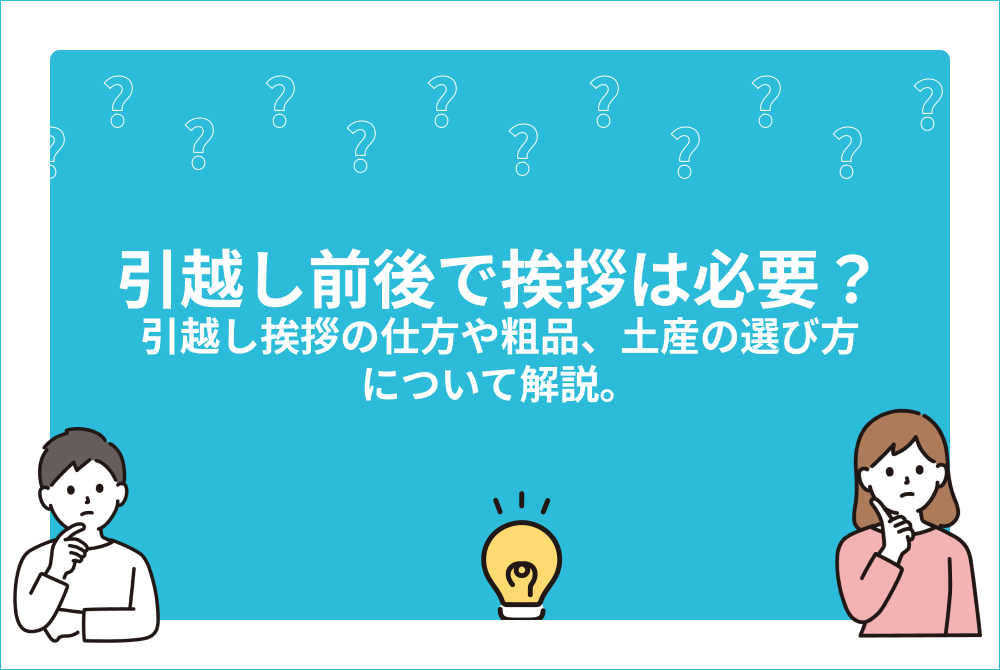
.png)