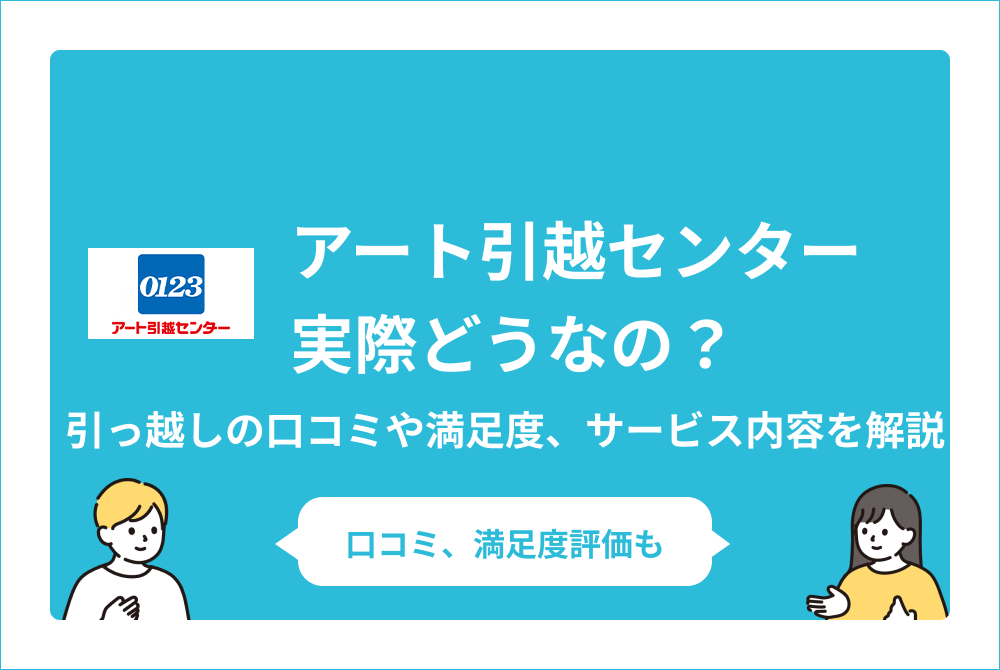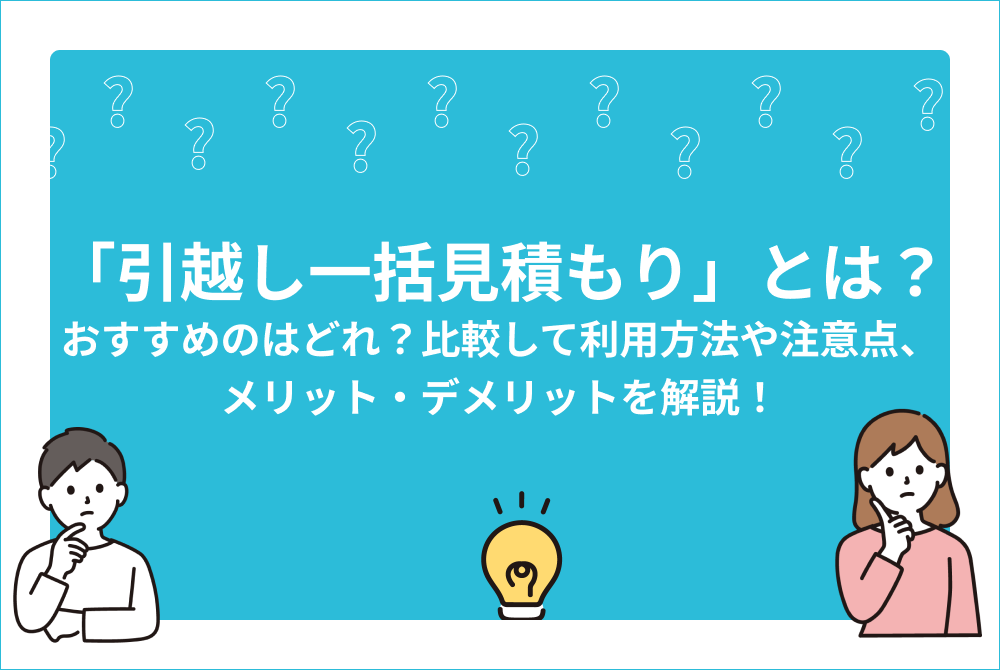目次・一覧
引越しを思い立ったはいいものの、いつまでに何をすればいいのかわからない方は多いのではないでしょうか。引越しは、前準備が最も大変だと言われています。特に初めての一人暮らしや、子育て中の家族の場合は、時間や手間を考慮しながら効率的に進める必要があります。そのためには、まず引越しで行うべきことの全体像を把握する必要があります。
この記事では、以下のことがわかります。
- 時期別に行うべき引越し準備内容
- 一人暮らしの方、家族向けの準備期間の目安
- 時期別のToDoリスト
引越し準備は早すぎてもダメ?遅れるとどうなる?最適な開始時期とは
引越し準備は、早すぎるのも遅すぎるのも、それぞれデメリットがあります。最適なタイミングを把握し、計画的に進めることが重要です。
早すぎる引越し準備のデメリット
早すぎる準備は、余計な手間や費用を生じさせてしまう可能性があります。例えば、引越し直前まで使う物を梱包してしまったり、どの箱に何の荷物が入っているのかわからなくなってしまう場合があります。
また、長期間引越し準備に集中してしまうと、プライベートに時間を割けなくなってしまいます。
遅すぎる引越し準備のデメリット
一方、準備が遅すぎると、時間的な余裕がなくなり、焦って作業を進めることで、ミスや見落としが発生しやすくなります。例えば、希望する引越し日時までに荷造りが終わらなかったり、業者への依頼が遅れて希望日が予約できなかったりする可能性も高まります。また時期によっては繁忙期と重なってしまい、費用が大幅にかさんでしまうこともあります。
最適な準備開始時期
一般的には、引越しの1ヶ月前~2週間前あたりから準備を始めるのがおすすめです。引越しの規模や状況によって前後しますが、1ヶ月~2週間ほどであれば、十分な時間をかけて荷物の整理から荷造り、手続きまで、着実に準備を進めることができます。特に初めての引越しや、家族での引越しの場合、1ヶ月前から始めることで、不慣れな手続きも余裕をもって対応できるでしょう。
【時期別】引越し準備ToDoリスト:1ヶ月前/2週間前/1週間前/前日/当日
ここでは、引っ越し業者を利用する想定で、引越し1ヶ月前から当日までのToDoリストを、引越し日までの段階ごとにご紹介します。各時期にやるべきことを把握し、計画的に準備を進めることで、スムーズな引越しを実現しましょう。
転居先決定後すぐ
- 新居の周辺環境の確認: 引越しに向けて新居周辺の道路環境や駐車スペース、新居のエレベーターの整備状況などを確認すると良いです。確認した情報は引っ越し業者への見積もり依頼の際に活用しましょう。
- 引越し業者へ見積もり依頼・契約: 3社以上の業者に見積もりを依頼し、料金やサービス内容を比較検討します。時間がない方の場合はオンライン見積もりサービスも活用すると便利です。依頼する業者が決まったら、早めに契約をしておきましょう。
- 新居の契約開始日の決定・初期費用の支払い: 引越し日と新居の物件が空くタイミングをもとに入居日を決めます。入居日が決まったら新居の初期費用額も決まるため、早めに支払っておきましょう。
- 引越しスケジュールの計画: 引越し日、業者選び、物件探しなど、まずは引越しをするうえで必須なものの選定・契約を進めていきます。そこで決まった日程から逆算し、残り の手続きや準備の計画を立てます。
- 現住居の退去連絡・駐車場の解約: 退去の通知期限は一般的には1か月前までです。管理会社へ退去の旨を連絡し必要な書類をもらいましょう。駐車場を借りている場合は併せて解約の連絡も済ませましょう。
- インターネット回線の移転手続き:現在契約している回線の継続か新しい回線の契約のどちらかの方法でインターネット回線を新居へ移転させます。新しい回線に契約する場合、開通工事の予約が込み合っている場合があるので早めに依頼しましょう。
- 新居の家具・家電の選定: 新たに購入する家具、新居へ運ぶ家具、処分する家具の三つに分類し、家具の選定を始めましょう。
~引越し1カ月前まで
- 不用品整理・処分: 燃えないゴミなどゴミの日の間隔が遠い場合があるので、早めに着手しましょう。不用品をフリマアプリやリサイクルショップを活用して売却すると引越し費用の足しになります。
- 粗大ごみの回収依頼: 現在住んでいる自治体に依頼します。回収日は2〜4週先になる場合もあるので早めに依頼をしておきましょう。
- 新居のサイズ確認: 窓、冷蔵庫の配置スペースなどのサイズを測り、家具の購入に役立てます。
- 新居の家具・家電の購入とだいたいの配置決め:新居のサイズをもとに家具を選びましょう。搬入経路やコンセントの位置も考慮し、家具の配置を事前に決めておくことで引越し当日の搬入がスムーズです。
- 梱包材の購入: ダンボールの他、ガムテープ、緩衝材、カッター、マジック、軍手、ドライバーセット、掃除セットを準備します。100均などで購入すると費用を抑えられます。
- 学校の転校・転入手続き: 担任の先生に転校の旨を伝え、現在の学校と転校先の学校から必要書類を集めます。場合によっては転入試験を行うところもあり、事前に転入の流れを把握しておきましょう。
~引越し2週間前まで
- 転居に伴う役所での手続き: 現住所で転出届、引越し先で転居届を提出します。また引越し手続きが必要なものとしては、児童保険、介護保険などがあります。職場の健康保険に加入していない人は国民健康保険も引越し手続きの対象になります。
- ライフラインの住所変更: 携帯電話、固定電話、NHK、衛星放送やケーブルテレビ、新聞などの定期配信サービス、電気、ガス、水道など。電気については引越しの一週間前までに住所変更の手続きが必要になります。
- ライフラインの使用開始手続き: 新聞などの定期配信サービス、電気、ガス、水道などは住所変更と併せて新居での使用開始日についても手続きをしましょう。なおガスについては開栓当日に立ち合いが必要になるので、開栓希望日を予約し、当日は予定を空けておきましょう。
- 使用頻度が低い物の荷造り開始: 普段は使わないものや季節的に使わないものであれば、早めにしまっても必要になることはないので、荷造りを始めましょう。
~引越し1週間前まで
- 転送サービスの申込: 郵便や宅配便など、引越し後に現住所に届く可能性のあるものを転居先の住所に届けてもらうサービスです。郵便物であれば最長1年間無料で使えますが、宅配便は有料となる場合があります。
- 【冷蔵庫を運ぶ方向け】食品の整理: 引越し当日に冷蔵庫の中身が完全に空になるように、食品の使い切り方法を計画します。
- 食器の荷造り開始: 食器は割れ物のため他の荷物とは分けた専用のダンボールに詰めます。運送時に破損しないよう、クッション材などを詰めるようにしましょう。
- 日用品の荷造り開始: 必要になる可能性もあるので、荷物を詰めても、引越し当日まではダンボールを閉めないようにしておくと良いです。
- 書籍類の荷造り開始: 書籍は重くなりやすいので、小さめのダンボールに詰めましょう。
- パソコンのデータのバックアップ: 重要なデータはクラウドやUSBにバックアップをしておきましょう。
- 新居の家具・家電の具体的な配置決め: ダンボールを運び込む場所も含め、引越し業者に適格な指示を出せるよう、配置を具体的に決めておきましょう。
- 近隣への引越しの挨拶: 挨拶の他、粗品も渡すとより丁寧です。
~引越し前日まで
- 【家電を運ぶ方向け】家電の運搬準備: 冷蔵庫、洗濯機は水抜きをしておく必要があります。石油ストーブを使っている場合は灯油を処理します。
- 残りの荷物をダンボールに詰める:当日に使う物を除いて、全ての荷物をダンボールに詰めます。
- 清掃・ゴミ出し:清掃を行い、出たゴミは前日までに出しておくようにしましょう。引越し業者にゴミを引き取ってもらうことはできない点に注意です。
- 貴重品の管理:貴重品は常に自分の手元で管理します。自分で運ぶ荷物に入れておきましょう。
- 引っ越し業者からの連絡の対応:引越し前日には引越し業者から、当日の詳細について最終確認の連絡があります。必ず対応し、事前に共有しておきたいポイントはこのタイミングで伝えておくと、当日スムーズです。
- 睡眠をしっかりとる: 引越し 当日は体力勝負です。睡眠をしっかりとって、万全な体調で当日を迎えましょう。
~引越し当日まで(旧居)
- 全ての荷物を詰める:当日分として出していた荷物も含め、全ての荷物をダンボールに詰め、封をします。
- 引越し業者対応:作業の流れや荷物の置き場所など、引越し業者からの質問があれば、都度答えましょう。
- ライフラインの完全停止:荷物の搬出が終わったら各ライフラインの元栓を閉めます。電気はブレーカーを落とし、ガスは元栓を閉め、水道は水滴が漏れないように蛇口を閉めます。
- 最終確認・清掃:忘れ物がないか最終確認を済ませ、引越し作業で生じた汚れを掃除します。ゴミを捨てることはできないので、簡単な掃除にとどめておきましょう。
- 鍵の返却:鍵の返却と同時に管理会社の人に部屋の状態を確認してもらいます。その際に傷や汚れがある場合は別途修繕費が請求されることがあります。
~引越し当日まで(新居)
- ライフラインの作動確認:電気・ガス・水道の中でガスのみ開栓に立ち合いが必要なので、業者の到着を待ってから対応しましょう。電気・水道はそのまま使えるので、ブレーカーを上げ、蛇口を操作して正しく作動するか確認しましょう。
- 近隣住民への挨拶:引越し作業に伴う騒音に対するお詫びの意図も兼ねているため、引越し作業前に行うようにしましょう。粗品も用意すると、より丁寧な印象です。
- 引越し業者対応:荷物の運び先、家具の設置場所などを指示し、他に業者から質問があればすぐに対応し、スムーズな引越し作業を実現させましょう。荷物を全て運び入れたら、破損・紛失がないか確認します。該当するものがあれば業者に補償を求めることができるので、報告しましょう。荷物の確認後、引越し完了の書類にサインします。
- 荷解き:寝具やカーテンなどすぐに使うもの、使用頻度が高いものから荷解きを進めます。
~引越し後2週間まで
- 全ての荷物の荷解き:引越しに使ったダンボールを処分するためにも、全ての荷物を出し、日常生活が遅れる状態にしましょう。
- 転居に伴う警察での手続き: 運転免許証の住所変更と、車庫証明の手続きを行います。車庫証明については、引越し後も同じ駐車場を使う場合でも住所に変更があれば再取得する必要があります。
- 転居に伴う運輸支局での手続き: 自家用車がある場合は、引越し先の運輸支局で車検証の住所変更を行います。期限は引越し日から15日以内です。
- 各サービス・関係先の住所変更: 住所変更が必要なものとしては主に、銀行、民間保険、クレジットカード、会員登録しているサービス、パスポート、勤務している会社などがあります。いずれも期限はありませんが、早めに行わないと重要なお知らせが届かない場合もあるので注意しましょう。
- 転居手続きの開始: 転出届、転居届、電気・ガス・水道の停止手続き、インターネット・電話回線の移転手続きなど、可能なものから手続きを開始します。市区町村役場やインターネットで手続きできるものもあります。
- インターネット回線の開通工事の立ち会い:インターネットの開通工事を申し込んだ場合は立会いの必要があるので予定を空けておきましょう。
状況別で見る準備期間の目安:単身・家族での違い
引越し準備期間の目安は、単身引越しと家族引越しで異なります。それぞれの状況に合わせて、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
単身引越しの場合
単身引越しの場合、荷物量が比較的少なく、荷造りや手続きも自分一人で行うため、準備期間は短い期間で済む傾向があります。一般的な目安としては、2週間~1ヶ月程度です。
- 2週間: 荷物が最少限で、荷造りや手続きに慣れている場合の目安です。平日は仕事や大学で忙しい場合は、週末に集中して準備を進める必要があります。
- 1ヶ月: 荷物量が標準的で、荷造りや手続きに不安がある場合。1ヶ月あれば、不慣れな手続きも、調べながら余裕をもって準備を進めることができます。
家族引越しの場合
家族引越しの場合、荷物量が多いので、家族全員分の荷造りや手続きが必要となるため、準備期間は長期間になる傾向があります。特に子供がいる場合は、転校手続きや子供のケアも必要となり、さらに時間を要します。一般的な目安としては、1ヶ月半~2ヶ月程度です。
- 1ヶ月半: 荷物が標準的で、家族全員が引越しに協力的な場合。協力し合いながら計画的に作業を進めることで、1ヶ月半で準備が可能です。
- 2ヶ月: 荷物量が多めで、小さな子供がいる場合や、荷造りや手続きに不安がある場合。 2ヶ月程度の準備期間があれば、日常生活の空いた時間で余裕をもって、引越し準備を進めることができます。
準備期間を左右するその他の要因
引越しの準備期間は、上記の単身・家族の違い以外にも、様々な要因によって左右されます。
- 引越し時期: 引越し業者の繁忙期(3月~4月、9月~10月)は、業者の予約が取りにくく、料金も高くなる傾向があります。早めの予約と準備が必要です。
- 物件の契約状況: 新居の契約や旧居の退去期限の関係で、準備期間が短くなってしまう場合があります。荷造りのオプションサービスがある場合は、間に合わなくなる前に利用を検討するのも良いでしょう。
- 仕事の忙しさ:: 仕事や学業が忙しい時期は、引越し準備に割ける時間が制限されます。事前に予測できる場合はその時期を避け、突発的に忙しい時期を迎えても引越しに間に合うように余裕をもって準備を進めておきましょう。
ご自身の状況を総合的に考慮し、余裕を持った引越し準備スケジュールを立てるほか、時にはオプションサービスなどにお金をかけることも、引越し成功の鍵となります。
まとめ
この記事では、引越し準備をいつから始めるのが最適か、時期別のToDoリスト、状況別の準備期間の目安について解説しました。
引越し準備を開始する最適なタイミングは、引越し人数・荷物の多さをはじめ様々な要素で決まります。早すぎる準備にはモチベーション維持の難しさや不要な作業の増加などの短所があり、遅すぎる準備には急な作業によるミスの増加や費用の増加などの短所があるので、あなたの状況に合わせたスケジュールを立てましょう。
執筆者

DOOR賃貸編集部
DOOR賃貸運営事務局






















.png)






.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
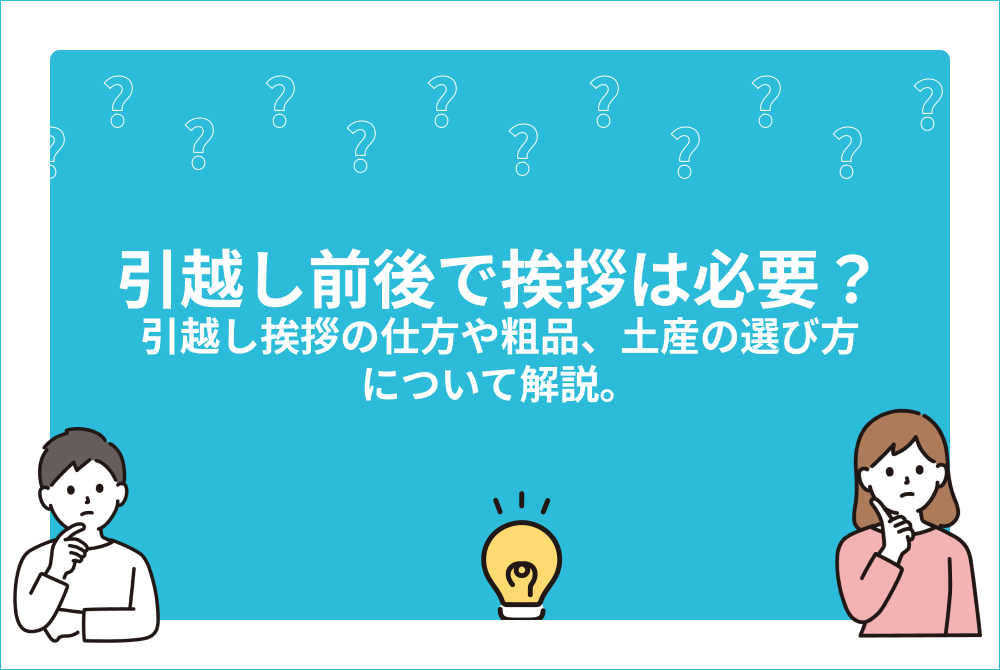
.png)