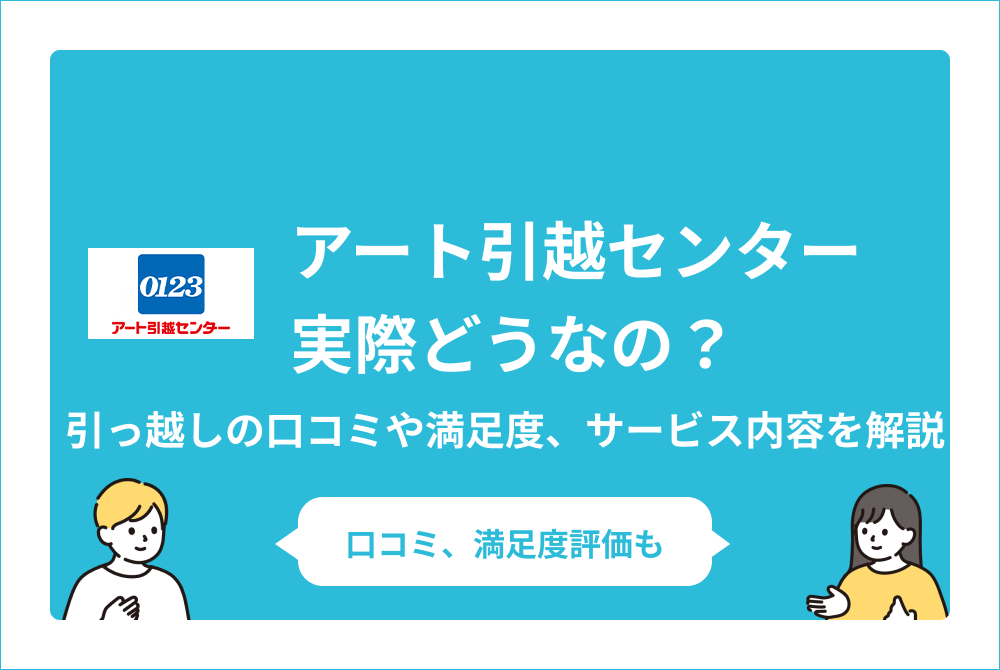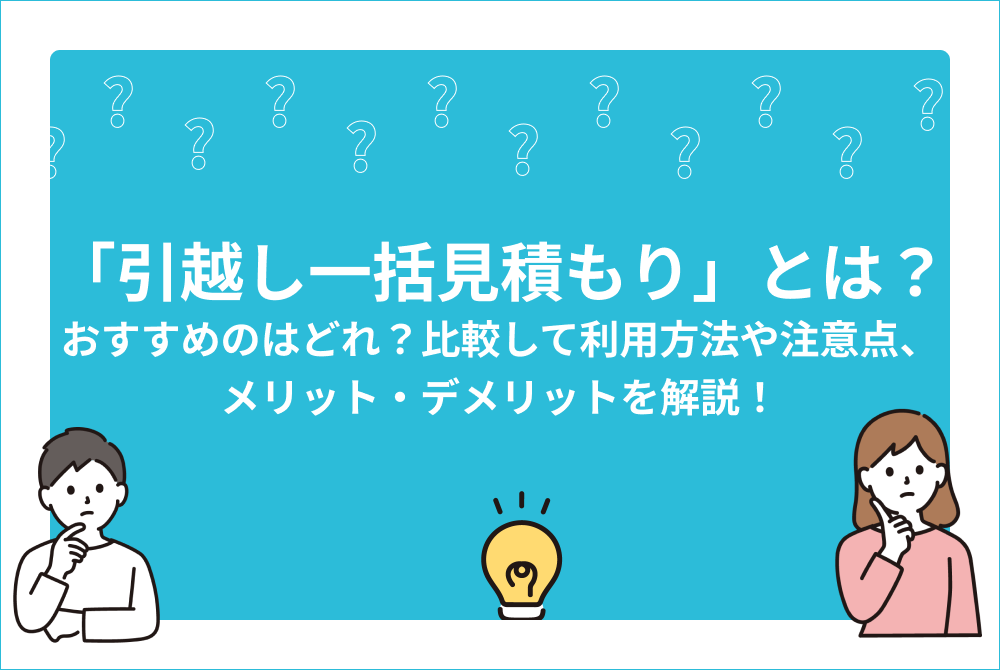目次・一覧
引越しといえば、準備が大変そうなイメージがあるのではないでしょうか。その中でも、役所での煩雑な手続きは誰もが苦労する準備の一つです。いつまでに何を手続きをすべきか、何の書類が必要なのかといった疑問だけでなく、最近ではマイナンバーカードが普及したことで、より悩みの種が増えたと感じるかたも多いでしょう。
そこでこの記事ではあなたの疑問を解決すべく、以下について解説します。
- 役所で行う手続きの全体像・スケジュールの立て方
- 各届出の手続き方法
- マイナンバーカードの手続き方法
役所の手続きは誰にとっても不安です。行うべきことを一つ一つ確認していき、万全の状態で引っ越しができるようにしましょう。
引越しで行う役所手続き:全体像と準備
引越しで行う手続きのスケジュールは、大きく分けて引越し前と引越し後の二つになります。なお対象者が全員となる手続きと該当者のみとなる手続きの二パターンがあるので、対象者別にスケジュールの全体像をおさえましょう。
引越しで必須の役所手続き
転出届・転入届・転居届の組み合わせは同じ市区町村内の引越しかどうかによって変わります。
引越し前の旧居の役所でやること- 転出届: 現在住んでいる市区町村から別の市区町村へ引越しする場合に必要です。
- 転入届: 転出届を出した際、新しい市区町村で提出します。
- 転居届: 同じ市区町村内で引越しをする場合に提出します。
- マイナンバーカードの住所変更: 住所が変わったら、マイナンバーカードの住所変更が必要です。
引越しで該当者のみが行う役所手続き
自身が該当する手続きがどれにあたるのか、確認しましょう。
引越し前の旧居の役所でやること- 国民健康保険の住所変更または資格喪失手続き
- 介護保険の住所変更または資格喪失手続き
- 児童手当の住所変更または受給事由消滅届
- 子どもの転園・転校手続き
- 印鑑登録の手続き
- 国民健康保険の加入手続き
- 介護保険の加入手続き
- 国民年金の住所変更手続き
- 児童手当の受給申請
- 子どもの転園・転校手続き
引越しで必須の役所手続き【転出届・転入届・転居届・マイナンバーカード】
転出届・転入届・転居届:違いと手続き方法、注意点
引越しを行う人が必ず行うべき役所の手続きは、転出届・転入届・転居届・マイナンバーカードの四つです。その中で転出届、転入届、転居届は場合によって届け出る組み合わせが異なるため、各届出の違いを整理しておきましょう。
転出届の手続きと注意点- どんな時に必要?: 現在住んでいる市区町村から、別の市区町村へ引越しする場合。海外へ引越しする場合も転出届が必要です。
- 手続き場所: 現在住んでいる旧居の市区町村の役所
- 手続き期間: 引越しの2週間前~引越しの当日
- 手続き方法: 窓口、郵送、ネット(マイナポータル)
- 必要なもの: 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、印鑑(認印でも可)、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証(加入者のみ)、マイナンバーカード(お持ちの方)
注意点:
- 転出届を提出すると、転出証明書が発行されます。転入届の際に必要になるので、大切に保管してください。なお郵送の場合は窓口やマイナポータルと比べて、転出証明書が手元に届くまでに時間がかかります。
- マイナンバーカードを利用して転出届を行った場合は特例転出の扱いとなるため、転出証明書は発行されません。マイナンバーカードの暗証番号が代わりとなります。
- どんな時に必要?: 転出届を提出し新しい市区町村に住み始めた場合。
- 手続き場所: 引越し先の新居の市区町村の役所
- 手続き期間: 引越しの当日~引越しの2週間以内
- 手続き方法: 窓口
- 必要なもの: 転出証明書(転出届を提出した際にもらったもの)、本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(加入者のみ)
注意点:
- 転入届は、必ず引越し後2週間以内に行う必要があります。期限を過ぎると、住民基本台帳法に基づき、最大5万円の過料に処される場合がありますので注意しましょう。
- マイナンバーカードを利用して転出届を行った場合は特例転入の扱いとなるため、転出証明書は発行されず、代わりにマイナンバーカードの暗証番号で手続きを行います。
- どんな時に必要?: 同じ市区町村内で引越しをする場合。
- 手続き場所: 引越し先の新居の市区町村の役所(同じ市区町村内の)
- 手続き期間: 引越しの当日~引越し後2週間以内
- 手続き方法: 窓口、ネット(e転居)
- 必要なもの: 本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード、国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
注意点:
- 転居届も転入届と同様に、引越し後14日以内に手続きを行わなければ、最大5万円の過料に処される場合があります。反対に引越し前は受け付けていないので注意しましょう。
- e転居は郵便局のサービスでオンラインで郵便物転送の手続きができます。一部自治体でのみ取り扱えるため提出先の自治体の取り扱い状況を確認しましょう。
転出届・転入届・転居届のケース別の組み合わせ
他の市区町村・都道府県へ引っ越す場合- 転出届:引越しの2週間前〜引越しの当日までに手続きを行います。
- 転入届:引越しの当日〜引越しの2週間後までに手続きを行います。
※海外へ引越す場合は海外転出届のみを渡航の14日前から当日までに提出しましょう。
- 転居届:引越しの当日〜引越しの2週間後までに手続きを行います。
マイナンバーカードの住所変更:オンライン手続きと注意点
マイナンバーカードを持っている方は、引越しに伴う住所変更の手続きが必須です。住所変更をしないまま放置すると、 e-Taxを活用したオンラインの確定申告や、健康保険証としての利用などの行政サービスが受けられなくなり、様々な不都合が生じる可能性があります。
マイナンバーカードは今後も様々な行政利用や民間サービスとの連携が予定されており、日常で使う機会はますます増えていきます。住所変更は必ず行っておきましょう。
マイナンバーカードの住所変更の手続きと注意点- どんな時に必要?: 引越しをする場合(同じ市区町村、別の市区町村へ引越した場合のどちらも)
- 手続き場所: 引越し先の新居の市区町村の役所
- 手続き期間: 引越しの当日~引越し後2週間以内
- 手続き方法: 窓口
- 必要なもの: 本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード、暗証番号
- 役所の窓口へ: 転入届または転居届の手続きと併せて、マイナンバーカードを窓口へ提出します。
- 暗証番号の入力: 窓口で暗証番号(数字4桁)を入力し、住所変更の手続きを行います。
- 券面事項変更: 職員がマイナンバーカードのICチップと券面情報を書き換えます。
- 【転入者のみ】継続利用手続き: 異なる市区町村へ移動しても同じマイナンバーカードを新居の市区町村でも引き続き利用するうえで必須です。
注意点:
- オンライン(マイナポータル)でも転入・転出・転居手続きの一部は行えますが、最終的に市役所へ来庁する必要があります。
- マイナンバーカードを利用し、インターネット上で行政サービスの登録・申請を行う場合は署名用電子証明書が必要です。住所変更手続きと併せて発行しておきましょう。
引越しで該当者のみが行う役所手続き【印鑑登録・国民健康保険・介護保険・国民年金・児童手当・転園・転校】
印鑑登録の手続きと注意点
- 対象者:新居で印鑑を登録を行いたい方
- どんな時に必要?: 他の市区町村内へ引越しをする場合。
- 手続き場所: 引越し先の新居の市区町村の役所
- 手続き期間: 基本的になし
- 手続き方法: 窓口、郵送
- 必要なもの: 本人確認書類、登録する印鑑
注意点:
- 転出届を提出することで印鑑登録の抹消は基本的に自動的に行われるので、手続きは不要です。例外的に行われない場合は、引越し前に旧居の市区町村で印鑑登録廃止届を提出しましょう。
- 抹消した印鑑の印鑑登録証(印鑑登録カード)は旧居の役所へ返却するか自身で処理しましょう。
- 市区町村によっては印鑑の有効期限が設定されている場合があります。引越し先の市区町村のホームページを確認しましょう。
国民健康保険の手続きと注意点
- 対象者:国民健康保険加入者(自営業者、学生など)
- どんな時に必要?: 引越しをする場合(同じ市区町村、別の市区町村へ引越した場合のどちらも)
- 手続き場所: 現在住んでいる旧居の市区町村の役所、引越し先の新居の市区町村の役所
- 手続き期間: 引越しの当日~引越し後2週間以内
- 手続き方法: 窓口、郵送
- 必要なもの: 本人確認書類、国民健康保険証、印鑑、転出証明書
【別の市区町村へ引越した場合】国民健康保険の手続き
- 旧居の役所の窓口へ: 資格喪失の手続きを行います。国民健康保険証を忘れないようにしましょう。
- 新居の役所の窓口へ: 再加入の手続きを行います。転出証明書を忘れないようにしましょう。
【同じ市区町村へ引越した場合】国民健康保険の手続き
- 新居の役所の窓口へ: 住所変更の手続きを行います。国民健康保険証を忘れないようにしましょう。
注意点:
- 引越し先が同じ市区町村であるかどうかに関わらず、手続き期間は引越しの当日~引越し後2週間以内です。
- 別の市区町村へ引越した場合の再加入手続きの際には、転出証明書を必ず提出しましょう。
介護保険の手続きと注意点
- 対象者:介護保険被保険者証を持っている65歳以上の方、要介護・支援認定を受けている方
- どんな時に必要?: 引越しをする場合(同じ市区町村、別の市区町村へ引越した場合のどちらも)
- 手続き場所: 現在住んでいる旧居の市区町村の役所、引越し先の新居の市区町村の役所
- 手続き期間: 引越しの当日~引越し後2週間以内
- 手続き方法: 窓口、郵便
- 必要なもの: 本人確認書類、介護保険被保険者証、印鑑、介護保険受給資格証
【別の市区町村へ引越した場合】介護保険の手続き
- 旧居の役所の窓口へ: 資格喪失の手続きを行います。介護保険被保険者証を忘れないようにしましょう。
- 新居の役所の窓口へ: 再加入の手続きを行います。印鑑と介護保険受給資格証を忘れないようにしましょう。
【同じ市区町村へ引越した場合】介護保険の手続き
- 新居の役所の窓口へ: 住所変更の手続きを行います。介護保険被保険者証を忘れないようにしましょう。
注意点:
- 引越し先が同じ市区町村であるかどうかに関わらず、手続き期間は引越しの当日~引越し後2週間以内です。
- 別の市区町村へ引越した場合の再加入手続きの際には、介護保険受給資格証を必ず提出しましょう。
国民年金の住所変更手続きと注意点
- 対象者:第1号被保険(自営業・農業者・漁業者・学生・無職)
- どんな時に必要?: 引越しをする場合(同じ市区町村、別の市区町村へ引越した場合のどちらも)
- 手続き場所: 引越し先の新居の市区町村の役所
- 手続き期間: 引越しの当日~引越し後2週間以内
- 手続き方法: 窓口、郵便
- 必要なもの: 本人確認書類、国民年金手帳、印鑑、介護保険受給資格証
国民年金の住所変更手続き
児童手当の住所変更手続き 転園の手続き
児童手当の住所変更手続きと注意点
転園・転校の手続きと注意点
- 所属園へ: 転園の旨を担任の先生に伝え、退園に必要な書類をもらいましょう。また旧居の役所へ行き、入学通知書を発行してもらいます。
- 転園先へ: 空き状況を確認し入園の申し込みを行います。園によっては面接や試験が必要になる場合もあるので、確認しましょう。
転校の手続き
- 所属校へ: 転校の旨を担任の先生に伝え、在学証明書と教科書給与証明書を発行してもらいましょう。
- 転校先へ: 指定された学校または希望の学校へ在学証明書、教科書給与証明書、入学通知書を提出します。私学の場合は面接や試験が必要になる場合もあるので、確認しましょう。
事前準備が大切!役所手続きのスケジュール一覧
これらの手続きをスムーズに進めるには、事前の準備が不可欠です。引越しが決まったら、まず「いつ、どこで、何の手続きが必要なのか」を把握しましょう。引越しは時間に追われることもあるので、早めの確認が重要です。
事前準備のポイント
- 必要書類の確認: 手続きごとに必要な書類を確認し、事前に準備しましょう。本人確認書類、印鑑、マイナンバーカードなどが一般的に必要です。各自治体のウェブサイトで確認するのが確実です。
- 期限の確認: 各手続きには期限があります。特に転入届は期限を超えてしまうと最大5万円の過料に処される場合があるので注意です。
- 手続き場所・時間の確認: 役所の窓口が開いている時間を確認し、時間に余裕をもって行きましょう。最近はオンラインでできる手続きも増えています。
各役所手続きの期限と特徴
| 手続き | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 転出届 | 引越しの2週間前~引越しの当日 | 郵送やオンラインで可能な場合もあります。 |
| 転入届/転居届 | 引越しの当日~引越しの2週間以内 | 遅れると過料が科せられる可能性も。 |
| マイナンバーカード | 引越しの当日~引越し後2週間以内 | 転入届提出後90日以内に手続き完了しないとマイナンバーカードが失効します。 |
| 印鑑登録 | 基本的になし(加入者のみ) | 印鑑登録の抹消は基本的に自動的に行われます。 |
| 国民健康保険 | 引越しの当日~引越し後2週間以内(加入者のみ) | 旧居と新居の手続きによって提出する書類が異なります。 |
| 介護保険 | 引越しの当日~引越し後2週間以内(加入者のみ) | 旧居と新居の手続きによって提出する書類が異なります。 |
| 国民年金 | 引越しの当日~引越し後2週間以内(加入者のみ) | マイナンバーと国民年金の基礎年金番号が紐付けられている場合は不要です。 |
| 児童手当 | 引越しの当日~引越し後15日以内(受給者のみ) | 旧居と新居の手続きによって提出する書類が異なります。 |
| 転園・転校 | 転園・転校先が決まり次(転園・転校者のみ) | 転園先・転校先によって提出する書類や手続き方法が異なります。 |
事前にしっかりと準備をしておくことで、当日の手続きがスムーズに進み、時間や手間を大幅に削減できます。特に、共働き夫婦や小さなお子さんのいる家庭では、オンライン手続きの活用を検討しましょう。
まとめ
引越し時の役所手続きは、種類が多くて大変ですが、一つずつ確実にこなしていけば、必ずスムーズに完了できます。
この記事で覚えておいてほしいポイント- 転出届は引越し前に、転入届・転居届は引越し後に
- 手続きは期限に余裕をもって行う
- マイナンバーカードの住所変更も忘れずに
- オンラインでできる手続きは積極的に活用する
引越し手続きをスムーズに終えて、新しい生活を気持ちよくスタートしてください! もし手続きで困ったことがあれば、役所の窓口で相談してみましょう。各自治体のウェブサイトには、詳細な情報や手続きの案内が掲載されていますので、そちらも参考にしてください。
執筆者

DOOR賃貸編集部
DOOR賃貸運営事務局






















.png)






.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
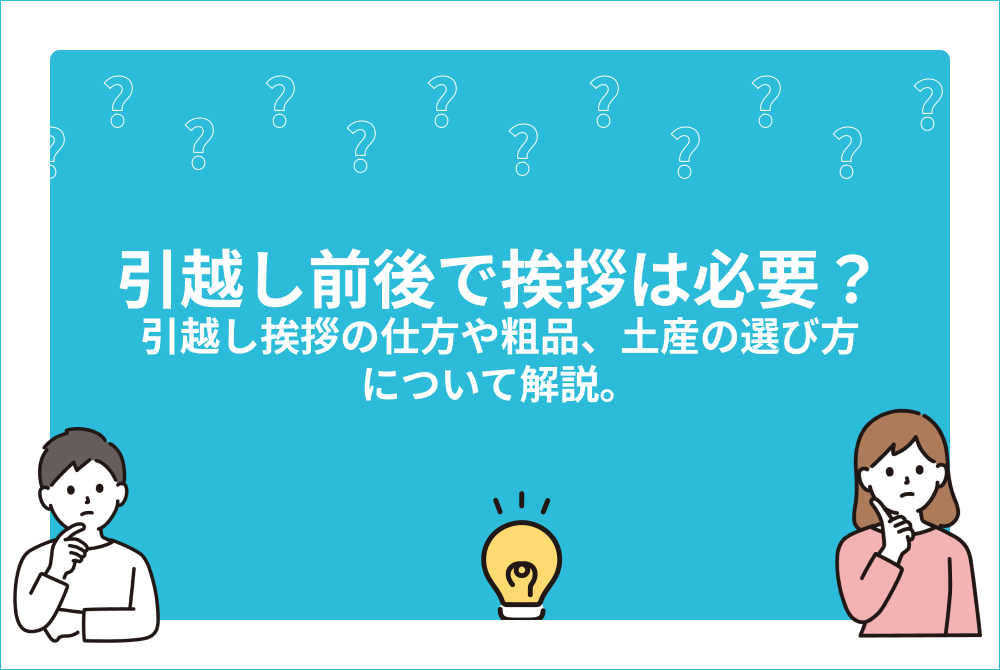
.png)